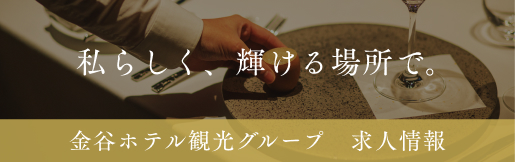issue 12
伝統とモダンの美をつなぐ
大谷石

鬼怒川金谷ホテルの各所に登場する大谷石。世界的な建築家フランク・ロイド・ライトも認めた和の銘石です。その魅力と歴史を石の里、栃木県宇都宮市大谷町に訪ねました。
幻想的な巨大地下空間「大谷資料館」
洞窟を冒険するみたいに、地下への階段を降りていくと、そこには広大な地下空間がありました。真夏でも肌寒いほど、しんしんと冷えます。四方の石壁には、地底から天井まで、びっしりと波跡のような模様が彫られ、地下水は虹色にライトアップされて、その巨大な空間自体がひとつのアート作品のように美しく、幻想的でした。

ここは、鬼怒川から車で50分程の、栃木県宇都宮市大谷町にある「大谷資料館」です。案内してくださった館長さん曰く、「ここは元々の大谷石の地下採掘場跡です。壁全体の模様は平場掘りや垣根掘りといわれる、職人たちが地上から地下へと何十年も石を掘り進んだノミの採掘跡なんですね」。
大谷石採掘の最盛期は昭和の高度成長期と重なります。コンサートホールが丸々入りそうな空間には、大谷石の歴史と採掘を物語る展示もあり、歴史のロマンと新たな発見にみちています。
あんなところに、ローマ時代の円柱のようなものが見えますが−。
「あれは、映画のセットですね。ここは資料館としてだけではなく、ロケ撮影や高級ヨーロッパ車のレセプション、企業イベントやアートスペースとしても使用されています。豊富な地下水の冷気を利用した自然のワインセラーや野菜保管庫でもあるんですよ」。


世界的な銘石、大谷石の歴史
「大谷石」の名が日本各地に知られるようになったのは、天平13年(795年)といわれます。国分寺建立の土台石として使われたのを始まりに、康平6年(1063年)に宇都宮城築城にも重用されました。以来、関東近圏の戦国城、寺社境内、さらには日光東照宮建立でも重用され、一般には石碑や墓石の石材としても有名になりました。
享保6年(1721年)には、江戸大川(隅田川)に16件の大谷石問屋があったという記録もあります。大谷石の運搬には舟運が用いられ、その主要な水路の一つが鬼怒川でした。

当時の大谷石の名声を物語るのが、大谷資料館からほど近い大谷寺の「大谷観音像」です。日本最古ともいわれるこの石仏は、東のガンダーラ像とも呼ばれています。
大谷石でできた御止山に抱かれるように建つ本堂の内奥、その岩肌に直接、仏様たちが彫られていました。平安時代の弘法大師空海作とも信仰される迫力ある千手観音像は、大谷石独特の温かみある表情を活かしたやさしいお顔だちながら、秘仏の神秘的なムードに包まれています。他に十躰の石仏が建立されていて、当時の大谷石工の熱意と技術の高さに圧倒され、感動するのです。
大谷石と鬼怒川金谷ホテル
主に伝統的な日本建築物に使われていた大谷石に、新たな魅力を発見したのが、アメリカ・モダニズム建築の巨匠フランク・ロイド・ライトでした。大正11年にライトが設計した旧帝国ホテルは、大谷石をふんだんに用いて建てられた世界初の西洋建築物でした。さらに意匠としてのみならず、大谷石でできたホテルは関東大震災に耐えてみせるなど、その耐火耐震性の高さを証明したのです。
そして、鬼怒川金谷ホテルの各所にも、大谷石が使われています。お客様をお迎えし、お寛ぎいただくロビーラウンジやダイニング、館内の柱などに使われる大谷石は、東洋と西洋の融合を果たしたモダニズム建築の進化形を意識したデザイン。国内ホテルでも、これほど贅沢に大谷石を用いたホテルは稀です。
また、大谷石の格調高い石肌は、料理プレートやコースター、キャンドルなど、鬼怒川金谷ホテルのおもてなしに欠かせないアクセントになっています。
大谷石のモダニズム精神は、伝統と革新をつなぐ鬼怒川金谷ホテルの旅の思い出をますます美しく彩ることでしょう。


2021年2月掲載

大谷資料館
所在地: 〒321-0345 栃木県宇都宮市大谷町909
当館より車で約50分※カーナビゲーションをお使いのお客様は、施設名称もしくは電話番号で検索して頂けますようお願いいたします。
営業日:4月~11月無休12月~3月毎週火曜日休館(火曜日が祭日の場合翌日休館)
臨時休館の場合がございますので、お電話でご確認ください
電話: 028-652-1232
SERIAL STORY
issue 29
たいせつなお客様に贈る、
ホテルクオリティの眠り。
issue 28
西形彩が彩る
金谷菓子本舗のビスケ
issue 27
清水の里が育む美食の魚
プレミアムヤシオマス
issue 26
日光田母沢御用邸
記念公園
-天皇家ゆかりの
美邸に遊ぶ
issue 25
酒蔵とホテルがつむぐ
新たなストーリー
issue 24
最上階の眺めのいい部屋
スイートルームの
優雅な魅惑
issue 23
シガーの薫香ただよう
旅の物語を紡ぐサロンへ
issue 22
奥日光の文化と
歴史を味わう
「煌めきのクラフトビール」
issue 21
心を揺さぶる
鬼怒川金谷の美食
感動を紡ぐ総料理長
issue 20
日光の昔ながらの酒造り
秘蔵の酒を探訪する
issue 19
大地と清流が育てる、
日光の奇跡の米。
issue 18
絶景を見晴らす、
新客室に癒されて。
issue 17
足をのばして霧降高原へ
issue 16
鬼怒川金谷ホテルの朝食
issue 15
スイーツワゴンで
甘美な夜を
issue 14
栃木が世界に誇る
「日光杉並木街道」へ
issue 13
ジョン・カナヤの愛した
ジョニーウォーカー
issue 12
伝統とモダンの美をつなぐ大谷石
issue 11
関東の名湯鬼怒川温泉の魅惑を紐解く。
issue 9
下野国の歴史ある名食、
「日光湯波」を味わう。
issue 8
伝統と未来を宿す、
美食の卵「金谷玉子」
issue 7
「光の巨匠」、
ガブリエル・ロワールの
芸術
issue 6
お客様の笑顔が
いちばんの幸せ
issue 5
シャンパーニュの皇帝
Champagne NAPOLEON
issue 4
金谷伝統の味わい
和風ビーフシチューの秘密
issue 3
鬼怒川渓谷の美と安らぎ
issue 2
ショコラティエ 野口和男氏
issue 1