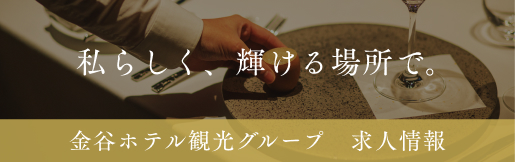盃と遊ぶ
詩人
石田瑞穂
旅にでるとき、人には思い思いの携行品がある。友人は旅行鞄にかならず馬毛の歯ブラシを二本いれる。べつの知人は「枕が変わると眠れなくて」という言葉通り家の枕をもってゆく。専用のドライヤーをキャリーバッグに収納する女性もおおいだろう。
ぼくの場合、それは旅の盃、である。
さきに書いた事例のごとく、愛用の盃を仕覆にいれて外出することは、ぼくにとってきわめて自然な行為なのだが…他人からみるとかなりヘンな習性らしい。
日本でも海外でも古本市と骨董市が大好きで、京都なら東寺縁日の弘法市、欧州ならマーケットに観光そっちのけで通う。以前、イギリスのポートベロの市で発条のとびだした柱時計に惚れこみ、日本まで抱えて帰った。
「どこでひろったの…」と家人は汚いモノでもみるように絶句。唯一、西欧骨董店の若い店主がおもしろがり買い取ってくれた。
写真の盃は、桃山時代の作と伝えられる古唐津山瀬窯盃。高台は酒徒好きのする半月型で、古木をすぱっと一刀両断したかの景色は武士の風格が漂う。山瀬特有の白んで細やかな土味。唐津焼特有のおおらかな轆轤で、すこし傾いだ容、胴についた古の陶工の指痕も好もしい。
山瀬のほとんどは筒盃だが碗形の盃は珍品。なにより無傷、完器。永年、酒を吸ってとろりと侘びた藁灰釉の肌。見込へと酒を注げば、釉溜の靄が青白く耀いて、唐津の美しく透明な海底を覗きこむような酔い心地である。
古唐津盃は酒徒にとって憧憬の盃なのである。
この山瀬盃を手にしたのが四年前。家族に内緒でなんとか金策し、高嶺の花をわが物としたときのうれしさ…すると、後日、先の持主から丁寧な礼状が届き、文通のなりゆきで南青山の鮨屋で逢うことになった。
唐津から遊びにきた蒐集家は、七十六歳の元日本史教師。酒を酌み交わし鮨をつまみながら、古美術誌「目の眼」でも特集された氏のコレクションにふれると、
「教員だったもんで、ボーナスの度こつこつ集めました。古唐津も昔の九州じゃ目をむくほど高くなかった。子どものころは裏山の窯跡で絵唐津の陶片をひろうたり、将棋の駒にして遊びよったしね。古唐津は幼馴染のようなもんで、いまでもみるにつけ唐津人の血が騒ぎます」
氏の手には「これだけは手放せんかった」という、美事に枯淡な皮鯨盃が愛おしそうに握られていた。
時空を超えて旅する盃の不思議。このちいさな土のうつわがなければ、縁もゆかりもない、関東平野と九州北端に暮らす男ふたりが出逢う一夕もなかったのだ…。
今宵もぼくは旅の宿で、山瀬盃の高台に小指をひっかけ、旨い地酒を呷る。そうして掌に馴染みつつある桃山の盃と、宿の料理のならぶ酒の景色が、自分の旅の重要なシーンになっていることに気づくのだった。

石田 瑞穂
詩人。代表詩集に『まどろみの島』(第63回H氏賞受賞)、『耳の笹舟』(第54回藤村記念歴程賞受賞)、新刊詩集に『Asian Dream』がある。左右社WEBで紀行文「詩への旅」を連載中。
「旅に遊ぶ心」は、旅を通じて日本の四季を感じ、旅を愉しむ大人の遊び心あるエッセイです。
ARCHIVES
2025 winter
秘湯と遊ぶ
2025 autumn
古道と遊ぶ
2025 summer
鰻と遊ぶ
2024 winter
美と遊ぶ
2024 autumn
時と遊ぶ
2024 summer
音と遊ぶ
2024 spring
青と遊ぶ
2023 winter
光と遊ぶ
2023 autumn
盃と遊ぶ
2023 summer
異邦人と遊ぶ
2022 autumn
ワインと遊ぶ
2022 summer
香と遊ぶ
2022 spring
愛車と遊ぶ
2021 winter
白と遊ぶ
2021 summer
酒精と遊ぶ
2021 spring
風と遊ぶ
2020 winter
幻と遊ぶ
2020 autumn
紅と遊ぶ
2020 summer
水と遊ぶ
2020 spring