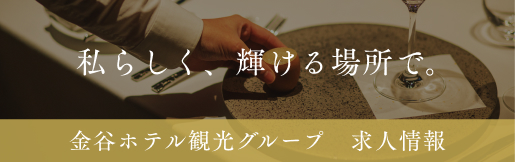青と遊ぶ
詩人
石田瑞穂
春の鬼怒川や奥鬼怒の山野を歩く愉しみは、梅桃桜、菜の花を愛でることのみならず、芽吹く若菜もおおいに悦びをあたえてくれる。
せり、なずな、ごぎょうではじまる春の七草はもちろんのこと、枯れ藪の枝先に青々と灯るたらの芽、棚田のふきのとう、路傍のぜんまいやわらびを発見するだに心踊る。江戸時代の大阪俳諧師、小西来山の詠むがごとく、
青し青し若菜は青し雪の原
と、ぼくは、春の息吹そのもののような青に浮かれ騒いでしまうのだ。
春菜の魅力は五感で味わえることにもある。色彩のみならず、山菜固有の心地好い苦味と芳香は、まさに「青し」と讃嘆せずにはいられまい。なにより、植物の赤ちゃんともいうべき、ちいさく儚い見目の愛らしさ。そうした特長ある春菜のなかでも、ぼくはつくしを愛する。土に生える筆という名も、詩人の魂をふるわすネーミングだし、あの宇宙的なフォルムをした胞子穂やそこから散る粒子状の胞子、食すときに大変な思いをしてとりのぞく袴さえ、じつにチャーミングなのだ。
卵黄に掻きまぜられし土筆
阿波野青畝の春の句は、即物としての俳味なら、土筆の玉子とじ。土筆のオムレツなんて逸品もよいかもしれない。けれども卵黄を一面に咲くたんぽぽやかたばみの花ととれば、春の野の美味しそうな情景が想い浮かぶ。
そんな春先の旅行で、ぼくが鬼怒川金谷ホテルにもちこんだのは、尾形乾山窯「春野角向付」(江戸時代)である。箱書は永楽善五郎。京焼の地にたっぷり間と余白をとり、とぼけて愛嬌ある絵付だが、大胆に描かれたぜんまいと比べ、土筆とすぎなは筆の命毛だけで繊細に描き込まれている。琳派らしい風趣で、若草の青も発色よい。
その器に、青山総料理長が若菜を盛り付けてくださった。器と料理が奏でる景色はまさしく松尾芭蕉翁高弟去来の、
老いの身に青みくはゆる若菜かな
である。乾山窯は平安貴族的な画調が大半だけれど、春の柔らかな新芽や山菜を盛るなら、このくらい肩肘はらず懐の深い絵図が好ましい…などと自讃の独酌。春の青を格別な肴に、栃木の銘酒で愉しく酔うのであった。

石田 瑞穂
詩人。代表詩集に『まどろみの島』(第63回H氏賞受賞)、『耳の笹舟』(第54回藤村記念歴程賞受賞)、新刊詩集に『Asian Dream』がある。左右社WEBで紀行文「詩への旅」を連載中。
「旅に遊ぶ心」は、旅を通じて日本の四季を感じ、旅を愉しむ大人の遊び心あるエッセイです。
ARCHIVES
2025 winter
秘湯と遊ぶ
2025 autumn
古道と遊ぶ
2025 summer
鰻と遊ぶ
2024 winter
美と遊ぶ
2024 autumn
時と遊ぶ
2024 summer
音と遊ぶ
2024 spring
青と遊ぶ
2023 winter
光と遊ぶ
2023 autumn
盃と遊ぶ
2023 summer
異邦人と遊ぶ
2022 autumn
ワインと遊ぶ
2022 summer
香と遊ぶ
2022 spring
愛車と遊ぶ
2021 winter
白と遊ぶ
2021 summer
酒精と遊ぶ
2021 spring
風と遊ぶ
2020 winter
幻と遊ぶ
2020 autumn
紅と遊ぶ
2020 summer
水と遊ぶ
2020 spring