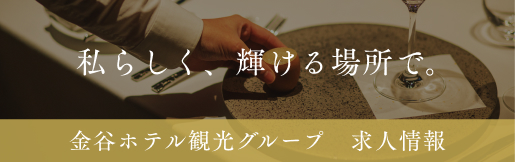鰻と遊ぶ
詩人
石田瑞穂
ここ数年、執筆の仕事で日光鬼怒川を訪れることがおおくなり、栃木の佳品にふれる機会も増えた。
日光の純米酒、味噌、醤油、やなの炉端焼で喰う鮎、米、川の温泉。どれも栃木の風土から生まれ、時を累ねてきた伝統の品々で、都会では出逢えない賜物ばかりだ。鬼怒川温泉郷への往来中、特急電車の車窓から眺める、日光の山裾までつづく広大な田園、いつまでも山の端に残照する夕焼け。ぼくの街ではとうに潰えた、古き善き栃木の山里が、胸を締めつける郷愁と安堵をもたらすのである。
先日も新たな旅の発見をした。
鬼怒川金谷ホテルで一泊した翌日。ぼくは栃木駅で下車し、〔蔵の街〕に遊んだ。巴波川の両岸に建つ白壁土蔵、木と大谷石の豪奢な和洋折衷様式で建てられた横山家を見て過ぎ、旧栃木町役場庁舎のライムグリーンの木造洋館まで散歩する。もとは銀行だったという、石の館のカフェで小憩した。いまも澄んだ巴波川を太った鯉が泳ぎ、高瀬舟が流れていく。ここにくると、大自然だけではない、商都栃木の文化と時の深さを実感するのである。
幸来橋でタクシーを拾い、その巴波川を藤岡方面へ。渡良瀬川べりの藤岡町、石川という字で下車した。
そこに、お目当ての鰻屋があった。大堤を降りてすぐの店である。渡良瀬川岸の柳林から涼風が吹いて、田んぼの水鏡に漣を生んだ。
いまは亡き祖父が、渡良瀬流域の佐野の出身で、鰻が好物だった。ぼくの鰻好きも祖父ゆずり。月に一度は浦和の老舗鰻屋で呑む。祖父のふるさとの川辺で鰻を味わいたかったのだ。
先附には甘露煮がでた。これも好い。祖父が「ざっこ」(雑魚)と呼んでいた田魚、コハゼ、コブナなどである。甘すぎず、川魚特有の蜜蝋めいた香と苦みが藤岡の〔新波〕という純米酒によくあった。身の締まった鯉の洗いにつづいて、鰻がいらした。地焼き、という備長炭で焼いただけの白焼き。鰻の脂本来の芳しさがたまらない。外側が音までぱりぱりに焼けているが、雪白の身は驚くほどしっとりと瑞々しい。
鰻は、静岡の吉田で養われる共水鰻、那珂川の天然鰻、だという。店主いわく「ガキの時分に食べた、渡良瀬の鰻の味がする」とか。重箱をはみだすようにのせられた鰻重はふっくらと蒸し焼かれ、表面が黄金色に照り輝いている。鰻は、口中で、米とともにとろけるようにほぐれた。
冷房のいらない、川風の通る店内。田からは凄まじい蛙声がし、渡良瀬川からは負けじと蜩がおこる。青空には悠々と白鷺。鰻を頬ばり、酒で雪ぎ、祖父と無言で呑みかわしている気がした。

石田 瑞穂
詩人。詩集に『まどろみの島』(第63回H氏賞受賞)、『耳の笹舟』(第54回藤村記念歴程賞受賞)など。最新詩集に『流雪孤詩』(思潮社)。
「旅に遊ぶ心」は、旅を通じて日本の四季を感じ、旅を愉しむ大人の遊び心あるエッセイです。
ARCHIVES
2025 winter
秘湯と遊ぶ
2025 autumn
古道と遊ぶ
2025 summer
鰻と遊ぶ
2024 winter
美と遊ぶ
2024 autumn
時と遊ぶ
2024 summer
音と遊ぶ
2024 spring
青と遊ぶ
2023 winter
光と遊ぶ
2023 autumn
盃と遊ぶ
2023 summer
異邦人と遊ぶ
2022 autumn
ワインと遊ぶ
2022 summer
香と遊ぶ
2022 spring
愛車と遊ぶ
2021 winter
白と遊ぶ
2021 summer
酒精と遊ぶ
2021 spring
風と遊ぶ
2020 winter
幻と遊ぶ
2020 autumn
紅と遊ぶ
2020 summer
水と遊ぶ
2020 spring