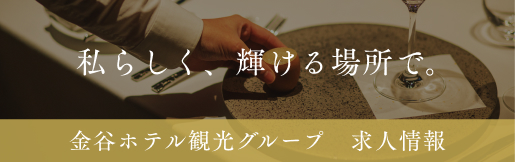古道と遊ぶ
詩人
石田瑞穂
『ワカコ酒』にも登場した北浦和のバー〔一滴水〕で、マスターが嬉々として語った。「こんどは白河から福島へ歩きます。一日四十キロの道程ですね」。バーの定休日に、マスターは松尾芭蕉の「奥の細道」を歩いて踏破することにチャレンジしている。蕉翁とおなじく、千住から歩きはじめ、四年かけて「白河の関」まできたのだった。
元禄二年(一六八九年)、四五歳の松尾芭蕉は門下の河合曾良と江戸を発ち、約百五十日かけて、下野、東北、北陸を旅してまわる。ぼくも雑誌の依頼で、日光街道草加宿の松原並木道や春日部宿の古落大利根川まで歩いたことがあった。そんなマスターの徒歩旅行は、ぼくの詩心にもゆっくりと火をつけていたらしい。好物のバラライカを呑みながら、いつのまにか、ぼくの旅の夢も野を歩きだしていた。
ある休日。ぼくは古びた京都〔一澤帆布〕のリュックを背負い、下野大沢駅から歩きはじめた。「奥の細道」にも登場し、今年、植樹四〇〇年を迎えた日光杉並木街道は、全長三五・四一キロメートル。今回は大沢町の並木寄進碑から東武日光駅まで歩き通す。
いまは車道の日光街道をゆき、今市宿の商店街をものめずらしく見て過ぎ、杉並木街道入口に立った。神錆びた杉の大木がどこまでもまっすぐ並ぶ古道は、江戸の往時のまま、といってよく、深閑と、清浄な空気につつまれている。深呼吸。歩くだけで、気が浄まり、活力がもどりそうな佳き道だ。鬱蒼としたところから、道のそちこちに、木漏れ日が落ちている。苔むした石垣にカワラナデシコの花がゆれる。ゆったり歩く旅だからこそ、気づく空間、味わう時間がある。四月に室の八嶋を通過した蕉翁はこんな句を詠んでいる、
あらたふと青葉若葉の日の光
日光杉並木の澄んだ風情のみならず、その道を草鞋で急ぐ、芭蕉と曾良の旅の高揚がよくつたわる句だ。
汗みずくになり、足は痛み、腿はぴくぴくふるえたが、観光客で賑わう日光東照宮に到着。旅のお礼参りをし、東武日光駅そばの鮨屋で打ち上げ。カウンターで干瓢巻きをつまみにビールをあおり、「大沢からここまで歩いた!」とあきれる大将をまえに、「次回は芭蕉の里、黒羽まで歩こうかしらん」となにげなくスマホを検索して、魂消た。
芭蕉と曾良の銅像の画像—蕉翁は馬に乗っていた。

石田 瑞穂
詩人。詩集に『まどろみの島』(第63回H氏賞受賞)、『耳の笹舟』(第54回藤村記念歴程賞受賞)など。最新詩集に『流雪孤詩』(思潮社)。
「旅に遊ぶ心」は、旅を通じて日本の四季を感じ、旅を愉しむ大人の遊び心あるエッセイです。
ARCHIVES
2025 winter
秘湯と遊ぶ
2025 autumn
古道と遊ぶ
2025 summer
鰻と遊ぶ
2024 winter
美と遊ぶ
2024 autumn
時と遊ぶ
2024 summer
音と遊ぶ
2024 spring
青と遊ぶ
2023 winter
光と遊ぶ
2023 autumn
盃と遊ぶ
2023 summer
異邦人と遊ぶ
2022 autumn
ワインと遊ぶ
2022 summer
香と遊ぶ
2022 spring
愛車と遊ぶ
2021 winter
白と遊ぶ
2021 summer
酒精と遊ぶ
2021 spring
風と遊ぶ
2020 winter
幻と遊ぶ
2020 autumn
紅と遊ぶ
2020 summer
水と遊ぶ
2020 spring